東京ディズニーシーの人気アトラクション「タワー・オブ・テラー」には、A・B・Cの3つのツアー(コース)が存在します。
それぞれのツアーにどんな違いがあり、どれが一番スリルを感じるのでしょうか?
また、ツアーの指定はできるのか、座る位置によって怖さは変わるのかも気になるところです。
この記事では、落下の回数や高さ・速度などの基本情報に加え、ツアーごとの特徴や一番怖い座席について詳しく解説しています。
これからタワテラに挑戦する方も、すでに体験済みの方も、ぜひ参考にしてください。
落下の回数・高さ・速度の違い
「タワー・オブ・テラー」は、恐怖演出が特徴のフリーフォール型アトラクションで、スリルを存分に味わえることで知られています。
このアトラクションにはエレベーターが設置されており、乗り場は1階と2階に分かれています。
1階と2階で体験に違いがあるのか、また怖さに差があるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
ここでは、1階と2階それぞれの落下回数や演出の違い、体験の差について詳しく解説していきます。
落下に関するデータは以下の通りです。
・落下回数:3回
・落下距離:35m
・落下時間:2秒
・落下速度:約50km/h
これらの数値をもとに、より詳しく見ていきましょう。
落ちる回数は基本3回
タワー・オブ・テラーでは、フェイントを含めて通常3回の落下が体験できます。
ただし、イベント時や特別バージョンでは、落下の回数が増えることもあります。
そのため、乗るたびに違った体験が楽しめるのも特徴です。
基本的には、3回落ちるパターンが一般的です。
落下距離はおよそ35m
ホテル・ハイタワーの建物全体の高さは59mありますが、実際にエレベーターが上昇する高さはおよそ35mです。
一部の情報では、落下距離が33mから38m程度と紹介されています。
目安としては、12階建てのビルに相当する高さと考えてよいでしょう。
ちなみに、日本で最も高いジェットコースターは、ナガシマスパーランドの「スチールドラゴン2000」で、その高さは97mです。
落下時間は最大2秒
落下にかかる時間は、最大で2秒ほどです。
この短い時間が人によっては長く感じられたり、あっという間に感じたりと、印象はさまざまです。
時速50kmで急降下
35mの高さを約2秒で落下することから、スピードはおよそ50km/hと計算されます。
他の資料では、50~60km/h程度と紹介されていることもあります。
参考までに、国内で最速のジェットコースターは富士急ハイランドの「ド・ドドンパ」で、最高速度は時速180kmです。
1階と2階の差はごくわずか
1階と2階の落下体験には、大きな違いはほとんどありません。
アトラクションには6つの乗り場があり、それぞれ効率よく運用されています。
わずかな高さの違いはあるものの、それが関係するのは主に最初と最後の動きのゆるやかな部分のみです。
体験全体としては、1階と2階に明確な差は感じにくい構造となっています。
ただし、体感には個人差がありますので、多少の違いが気になる方もいるかもしれません。
気になる場合は、両方の階を体験してみるのも良い方法です。
最も怖いのはツアーA
続いて、A・B・Cのツアーの中で、一番怖いとされるコースについてご紹介します。
タワー・オブ・テラーには3基のエレベーターがあり、建物を正面から見て左から順にA・B・Cと名付けられています。
何度も乗ってきた私の実体験からお伝えすると、最も怖いと感じるのはツアーAです。
このアトラクションの醍醐味は、ふわっとした無重力のような感覚ですが、ツアーAでは特にそれが強く感じられます。
私は1年間通い詰めて繰り返し体験し、ツアーAだけが他と異なる感覚をもたらすと気づきました。
Aは部屋の構造が異なる
A・B・Cのツアーのうち、ツアーAだけは演出の構造に大きな違いがあります。
具体的には、ハイタワー三世の部屋と鏡の部屋の配置が、他の2つと逆になっています。
ツアーAでは、下に鏡の部屋、上にハイタワー三世の部屋があります。
一方、BとCでは、下がハイタワー三世の部屋で、上が鏡の部屋になっています。
この配置の違いにより、エレベーターの昇降の距離と動き方に差が出ます。
BとCでは、1階分だけ上昇してハイタワー三世の部屋へ進み、さらにもう1階分上がって鏡の部屋へ向かいます。
対してAでは、まず2階分上昇してハイタワー三世の部屋に到達し、その後1階分下がって鏡の部屋へ向かう構造です。
このように、「書斎と鏡の部屋の位置が逆」という点が、ツアーAならではの特徴となっています。
Aの方が上昇が速い
部屋の配置が異なることにより、ツアーAでは移動距離が長くなるため、エレベーターの昇降速度も速くなっています。
どのツアーも所要時間は同じですが、Aではその時間内に長い距離を移動する必要があるため、スピードが上がる仕組みです。
ツアーAでは、最初にハイタワー三世の部屋へ向かって上昇します。
この部屋は、BとCよりも高い位置にあるため、その分長く上昇することになります。
その後、鏡の部屋に向かって1階分降下します。
上昇と下降の速度が速いため、途中で急ブレーキがかかるタイミングで、ふわっとした浮遊感がより強くなります。
ツアーAでは、加速と減速のメリハリが激しいため、他よりも強い恐怖を感じやすくなっています。
この浮遊感は、「慣性の法則」によって説明できます。
エレベーターが急に上昇し、突然止まると、身体は上へ動き続けようとします。
そのため、シートベルトに押さえつけられるような感覚とともに、強烈なマイナスGが発生します。
ツアーAではBやCよりも上昇スピードが速いため、そのぶんマイナスGも大きくなります。
また、鏡の部屋から最上階に向かう距離も長くなることで、最高地点に到達した時の浮遊感が一層強まります。
BとCは似た動き
他のウェブサイトでも解説されていますが、私の経験から言えば、ツアーBとCの動きには大きな差は見られません。
私は2017年から2018年にかけて年間パスポートを使って何度も乗りましたが、その中でもBとCの感覚はほぼ同じでした。
唯一の違いとして挙げられるのは、「ハイタワー三世の書斎と鏡の部屋の配置が反対になっていない」という点だけです。
それ以外は、動きや演出、浮遊感の強さなどもほぼ同じと言ってよいでしょう。
一番怖いのは後列中央の席
タワー・オブ・テラーでは、一度に22人の乗客がエレベーターに搭乗します。
その中で、どの席が最も怖さを感じやすいのかを見ていきましょう。
座席は前列7席、中列7席、後列8席に分かれています。
入口ドアは前方中央にあり、中央に階段がある構造です。
左右に分かれて3人または4人ずつ座りますが、後列中央には通路がなく、直接座席が設けられています。
《エレベーター内の座席配置》
〇〇〇〇◎〇〇〇
〇〇〇〇 〇〇〇
〇〇〇〇 〇〇〇
ーーードアーーー
この◎で示した後列中央の席が、最もスリルを感じやすいとされています。
前列にも怖さはありますが、すぐ目の前に壁があることで多少の安心感を得られます。
一方、後列中央の席は前が開けており、まるで空中に放り出されるような感覚が味わえるのです。
とことんスリルを楽しみたい方には、この席がおすすめです。
反対に、怖さを少しでも軽減したい方には、後列や中列の端の席が向いています。
壁が近くにあることで安心感があり、他の人の様子も視界に入るため、気持ちが落ち着きやすくなります。
ツアーの種類は選べない
タワー・オブ・テラーでは、A・B・Cいずれのツアーに乗るかを自分で選ぶことはできません。
どのツアーに案内されるかは、キャストの指示に従う形になります。
中には「Aに乗りたい」「Bがいい」と希望を伝える人もいますが、混雑の原因になるため対応が難しいことが多いです。
混雑状況や安全管理の都合上、スムーズな運営を優先するため、ツアーの指定は基本的に受け付けていません。
また、新たに導入された演出などでは、どのツアーになるかが事前に分からないようになっている場合もあります。
そのため、どのコースに乗れるかは、まさに運次第と言えるでしょう。
タワテラの建物正面には、4つの縦長の窓があります。
このうち、左端がA、その右隣がB、右端(左から4番目)がCに該当します。
真ん中にある残りの1つの窓は、実際には使用されていないダミーの窓です。
エントランスで列が進むと、キャストが「ツアーAへお進みください」などと案内してくれます。
進行方向は以下のようになります。
・左へ進むとツアーA
・まっすぐ進むとツアーB
・右へ進むとツアーC
それぞれの待機列には「tour A」「tour B」「tour C」と明記された看板があるので、分かりやすくなっています。
さらにアトラクションの途中で、1階と2階に分かれることもあります。
これはA・B・Cそれぞれに、1階と2階の乗り場が存在しているためです。
ただし、たとえ同じツアーAでも、1階と2階で大きく内容が異なるということはありませんので安心してください。
どのツアーになるかは、列に並びながらのちょっとしたお楽しみとして、受け止めると良いでしょう。

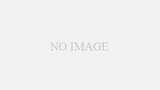
コメント