夏の夜空を華やかに彩る花火大会は、多くの人にとって特別な季節の楽しみです。
しかし、台風や大雨、強風、地震などの影響で、直前に中止となることも少なくありません。
そうなると、準備されていた花火や集めた協賛金、購入済みの有料席チケットなどがどうなるのか、気になったことはありませんか?
この記事では、花火大会が中止になった際に発生する経済的な損失、残された花火の扱い方、協賛金やチケット代の返金に関するルールについて詳しく解説します。
さらに、損失補填に利用される「興行中止保険」の仕組みや、リスクを減らすための具体的な対策も、実際の事例を交えてご紹介します。
花火大会が中止になったらどうなる?
夏の風物詩ともいえる花火大会は、多くの人が心待ちにしているイベントです。
ところが、台風や大雨、地震などの自然災害に加えて、強風や河川の増水など安全面の理由により、開催直前で中止になることも珍しくありません。
実際に2024年の夏には、全国で33か所の花火大会が中止または延期となりました。
なかには、宮崎県小林市のように後日開催できたケースもありますが、多くの大会ではその年の開催が完全に取りやめとなっています。
そうなると、準備されていた花火や協賛金、すでに販売されたチケットなどはどう扱われるのでしょうか?
中止による経済的な損失
花火大会は一夜限りのイベントではありますが、開催までには数か月から1年以上の準備期間と多額の費用がかかります。
会場の設営や仮設トイレの設置、照明・音響機材の準備、警備や交通整理の人員手配など、さまざまなコストが発生します。
たとえば足立の花火大会では、およそ2億7,000万円の予算が組まれていましたが、悪天候によって中止に・・・。
返金対応や準備費用を含めて、3,000万円以上の損失が出たと報告されています。
また、秋田県で開催予定だった「本荘川まつり花火大会」でも、大雨による中止で約1,000万円の準備費用が回収できず、最終的な損失は約1,140万円に達しています。
このように、中止は主催者側にとって大きな打撃となるだけでなく、来場者による消費がなくなることで地元の飲食店や宿泊施設などにも影響が及びます。
中止で残った花火はどうするのか?
花火大会が中止になった場合、用意された花火がどう処理されるかは、中止のタイミングによって変わります。
打ち上げ準備前の状態の場合
打ち上げの準備がまだ行われていない状態であれば、花火玉は乾燥したまま保管されているため、次回の花火大会や他のイベントで再利用できることが多いです。
特に高価な花火は、できる限り再使用される傾向にあります。
すでに現地で設置されていた場合
一方で、すでに会場で仕掛けが完了している場合は、雨や湿気の影響を受けてしまうことがあります。
湿気を吸った花火は、安全上の問題からそのまま打ち上げることができず、再利用も難しくなります。
このような場合は、専門業者によって水に浸して不活性化したうえで焼却処分されるなど、安全に配慮した方法で処分されます。
状況によっては、打ち上げにかかる費用以上の処理コストがかかることもあります。
神奈川県清川村では、台風で中止になった花火を翌月のイベントで再使用できた例もありますが、これは保管状態が良好だったためです。
反対に、ゲリラ豪雨の影響で中止されたある企業協賛の花火大会では、湿気により全ての花火が使用不能となり、協賛企業が処分費用を負担することになったケースもあります。
協賛金やチケット代は返金されるのか?
花火大会に協賛している企業や個人にとって、中止となった場合の返金対応はとても重要な関心事です。
多くの大会では、あらかじめ「中止となっても協賛金は返金しない」という条件が契約や規約に明記されています。
そのため、個人で数万円を協賛した場合でも、大企業が数百万円を出資していた場合でも、返金されずに損失となることがほとんどです。
一方、有料観覧席のチケットについては、主催者側の判断や販売時の規約によって対応が分かれます。
全額返金される場合もありますが、一部のみ返金、あるいは返金が一切行われない場合もあります。
返金の可否は、主催者が加入している保険の有無や、契約に盛り込まれた条項に大きく左右されます。
興行中止保険による補償制度
花火大会の主催者は、予測できないリスクに備えて「興行中止保険」に加入することがあります。
この保険は、悪天候や災害などでイベントが開催できなくなった際に、発生した損失の一定割合を補填してくれるものです。
一般的に、損失額の8~9割が補償されるケースが多く、保険料は保険金額の約1割程度が目安とされています。
ただし、保険に加入していたとしても、すべての損失を補填できるわけではありません。
補償対象外の費用や、関係者の労力、準備にかけた時間などは金銭的にカバーできないため、完全な回復は難しいのが現実です。
興行中止保険以外のリスク対策
花火大会は自然環境の影響を受けやすいため、主催者は興行中止保険に加えて、さまざまな方法でリスクを軽減しようとしています。
ここでは、代表的な3つの対策をご紹介します。
予備日(順延日)を設ける
最も一般的な対策は、事前に予備日を設定しておくことです。
予定日に悪天候などで開催が難しくなった場合、翌日や数日後に順延して実施することができます。
このようにすれば、準備した花火を無駄にせず打ち上げることが可能です。
ただし、順延によって観覧客のスケジュール調整が必要になったり、スタッフや設備の再手配が必要になるなど、主催側には追加の手間と費用がかかります。
また、予備日があっても天候の回復が見込めない場合は、結局中止となる可能性もあります。
規模を縮小して実施する
近年では安全を確保したうえで、規模を縮小して開催するという選択をする大会も増えてきました。
たとえば、強風が予想される場合は、高く上がる大型花火を避けて、低めの安全な花火だけを使用する。
また、河川の増水がある場合には、観覧エリアを一部制限したり、打ち上げ数を減らして対応することもあります。
こうした方法により、完全中止に比べて経済的な損失を抑えることが可能になります。
打ち上げ数の調整
天候が不安定なときや、安全面に不安があるときは、打ち上げる花火の数そのものを減らす判断がされることもあります。
予定よりも短時間で終了するプログラムにすることで、急な天候変化のリスクを軽減しつつ、最低限の演出を行うことができます。
ただし、こうした対応は観覧者の満足度に影響する可能性もあるため、事前にしっかりと説明や案内を行うことが求められます。
花火大会中止による地域への影響
花火大会は地域にとって、経済的にも文化的にも大きな役割を果たすイベントです。
観光客による宿泊や飲食の需要、交通機関の利用促進、地域ブランドの発信など、多くの経済効果が期待されます。
しかし、中止になることでこれらの効果が失われてしまい、特に地方都市や観光地にとっては深刻な打撃となります。
さらに、花火大会は地元住民の交流の場であり、地域の伝統や誇りともいえる存在です。
そのため開催できないことによって、精神的・文化的な損失も無視できません。
まとめ
花火大会が中止になると、主催者だけでなく、協賛企業や地域経済にも大きな影響が及びます。
用意された花火は保存状態によって再利用されることもありますが、雨や湿気の影響で処分が必要になることもあります。
協賛金やチケット代は、規約により返金されないケースが多く、主催者は興行中止保険によって一部の損失をカバーするものの、完全な補填は難しいのが現状です。
花火大会は常に天候リスクを伴うイベントであるため、来場者も返金規定や中止時の対応について事前に確認しておくことが大切です。
主催者・観客ともにリスクを正しく理解し、万が一の事態にも備えておくことが、トラブルを防ぐうえで重要です。

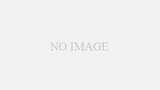
コメント