将棋界ではこれまで、一人も女性のプロ棋士(四段以上)が誕生していません。
一方で、女流棋士として活躍する女性は数多く存在し、毎年のようにタイトル戦で注目を浴びています。
見方によっては「女流棋士=女性のプロ棋士」と思われがちですが、実際には制度や昇段基準、競技レベルなどに大きな違いがあります。
では、なぜ女性は将棋で男性に勝てないとされるのか?
そして、なぜ今もなお女性プロ棋士が生まれていないのか?
この記事では、将棋界の制度構造や心理的要因、競技人口の男女差。
さらに過去に挑戦した女性奨励会員の事例をもとに、女性プロ棋士が誕生しにくい背景を多角的に解説します。
女性四段が未誕生の背景とは?
将棋界における「プロ棋士」とは、日本将棋連盟が認定する四段以上の棋士を指します。
プロ棋士になるためには、まず奨励会と呼ばれる育成機関に入会し、三段まで昇段した上で、さらに三段リーグという厳しいリーグ戦を戦い抜く必要があります。
この三段リーグは半年ごとに行われ、40名前後の参加者が15局を戦い、成績上位2名だけが四段に昇段できます。
年間の昇段者はおよそ4人程度と、非常に限られた枠しかありません。
こうした厳しい条件の中、全ての奨励会員は文字通り人生を懸けて対局に臨んでいます。
しかし2025年現在、このルートを突破して四段になった女性はまだ一人もいません。
過去には三段まで到達した女性も数名いましたが、奨励会には26歳までに四段に昇段できなければ退会という年齢制限があるため、惜しくも退会となっています。
中でも最も四段に近づいたのは西山朋佳さんで、三段リーグで2度も12勝3敗の好成績を残し、あと1勝で昇段という次点(3位)を記録しました。
また、西山さんと里見香奈さんは、棋戦成績によりプロ編入試験の挑戦資格を獲得し、プロ棋士5名との対局に臨みましたが、昇段には至りませんでした。
このように、女性がプロ目前まで迫った事例は存在するものの、最終的な壁を越えることはまだ実現していないのが現状です。
女流棋士とプロ棋士の制度差
将棋界には「女流棋士」という制度がありますが、これはプロ棋士とは全く異なる仕組みです。
女流棋士とは、女性を対象にした独自の昇段制度に基づき認定される棋士で、日本将棋連盟や日本女子プロ将棋協会が管理しています。
女流棋士は女流タイトル戦や、女流棋戦に出場することができます。
一般的に女流棋士になるためには、研修会と呼ばれる機関でB1クラスに昇級することが必要です。
研修会B1は、奨励会でいえば6級程度の棋力とされ、プロ棋士を養成する奨励会に比べると難易度は低めです。
一方、プロ棋士になるためには奨励会を経て三段リーグを勝ち抜かなければならず、その難易度は比べものになりません。
つまり、同じ「プロ」と呼ばれる立場でも、女流棋士とプロ棋士では制度の目的や昇段の難易度、競技レベルが大きく異なっています。
そのため「女流棋士=女性のプロ棋士」と誤解されることもありますが、実際には全く別の制度です。
また、両者が同じ棋戦で対局することもありますが、基本的には棋戦も制度も別であり、女流タイトルをいくつ持っていても、それだけでプロ棋士にはなれません。
この制度の分離は、女性に将棋界で活躍する道を広げる一方で、“別ルートがある”という特殊な状況を生み出しています。
そして、この存在が心理面や覚悟の差に影響しているとも考えられるのです。
女流制度が生む選択肢の影響
奨励会に在籍する女性にとって、女流棋士制度の存在は一種の“逃げ場”になっていると考えられます。
これは否定的な意味ではなく、制度として実際にそうした選択肢が用意されているという事実に基づくものです。
奨励会には「26歳までに四段に昇段できなければ退会」となる厳しい年齢制限があります。
この期限は男性奨励会員にとっても大きなプレッシャーであり、とくに三段リーグに在籍している人は、残されたわずかなチャンスに全力を注ぎ、文字通り命懸けで戦っています。
四段に昇段できなければ、長年の努力や時間が一瞬で失われるという過酷な世界です。
一方、女性には奨励会に在籍しながら、女流棋士になる道が認められています。
たとえば三段リーグで苦戦している女性も、女流棋士に転向すれば将棋界に残りながら第一線で活躍できます。
実際、福間香奈さんや西山朋佳さんは奨励会を経て女流棋士となり、数多くの女流タイトルを獲得しました。
奨励会を退会した瞬間から、女流将棋界のトップに立てる可能性がある制度設計なのです。
このため、「四段になれなければ女流になればいい」という考えが無意識に芽生えやすくなります。
それによって、男性奨励会員のような「絶対に後がない!」という覚悟を持ちにくくなり、本気度に差が生まれてしまうと指摘されています。
男性奨励会員には女流のような別制度はなく、三段リーグを勝ち抜く以外にプロになる道はありません。
逃げ場がないからこそ、必死さが極限まで高まり、それが結果にもつながります。
この「選択肢の有無」が、男女の覚悟の差に直結している可能性が高いのです。
女性奨励会員が抱える迷い
奨励会にいる女性は、常に「三段リーグで四段を目指すか、それとも女流棋士に転向するか」という二択を突きつけられます。
この選択肢があること自体は制度上の自由ですが、勝負の世界ではその存在が迷いとなって現れることがあります。
三段リーグに在籍できる力がある時点で、女流棋士としてはトップクラスの実力を持っていると見なされます。
事実、福間香奈さんや西山朋佳さんは三段リーグ経験を経て女流棋士になった後、すぐに女流タイトルを獲得し、女流将棋界を牽引する存在となりました。
こうした成功例を目の当たりにすると、
「この実力があれば女流でも十分やっていける」
「厳しい三段リーグにこだわる必要はないのでは」
という気持ちが生まれやすくなります。
さらに、周囲からも「女流にならないの?」や「もう十分強いのに、なぜ奨励会に残るの?」といった言葉をかけられることもあります。
悪意のない発言でも、本人の心を揺さぶる要因になり得ます。
プロ棋士になるには、この迷いに打ち勝ち、何度も「女流にならない」という決断を繰り返す必要があります。
しかし、迷いが心にあると、終盤で攻めを貫ききれなかったり、勝負所で一歩引いてしまったりすることもあります。
男性奨励会員にはこうした迷いの余地がなく、四段昇段だけを目指して全力を尽くせる環境があります。
この“選べてしまう苦しみ”が、女性奨励会員にとって大きな心理的負担となっているのです。
男女差からくる心理的負担
女性奨励会員が抱える、もう一つの心理的ハードルが「負い目」です。
これは、自分には女流棋士という逃げ道がある一方で、男性奨励会員にはその選択肢がないことから生じます。
三段リーグは限られた昇段枠を争うサバイバルの場であり、誰かが昇段すればその分ほかの誰かが道を絶たれます。
そこで女性が勝ち進んだ場合、
「自分が勝つことで男性奨励会員のプロ昇段のチャンスを奪ってしまうのでは?」
「自分には女流という安全な道があるのに、同じ土俵で戦っていいのだろうか?」
といった感情が芽生えることがあります。
本人が意識していなくても、この無意識の“遠慮”や“ためらい”が将棋の内容に影響を与えることは否定できません。
一手の迷いが命取りになる三段リーグにおいて、こうした心理の揺らぎは致命的です。
男性奨励会員は、負ければ即プロへの道が閉ざされるという状況で戦っています。
それに対し、「負けても女流として活動できる」という思いが少しでもあると、集中力や覚悟に差が生まれる可能性があります。
この負い目も、女性がプロ棋士になるための大きな壁の一つとなっています。
男女で異なる競技人口と環境
将棋界における男女比は極端に偏っており、競技人口の大多数が男性です。
将棋を趣味や競技として続けている女性はごくわずかで、この差はプロ棋士を目指す段階でも顕著に現れます。
奨励会に在籍する女性は常に数人程度しかおらず、その中で三段リーグまで到達する人はさらに稀です。
一方、男性は小学生の頃から将棋教室や大会で鍛えられ、全国各地に奨励会入りを目指す層が多数存在します。
分母が大きければ、それだけ突出した才能を持つ人が現れる確率も高まります。
これはスポーツや学問など、あらゆる分野に共通する現象であり、将棋も例外ではありません。
また、この競技人口の差は環境面や心理面にも影響を与えます。
将棋に本気で取り組む女性は、同世代で同じ目標を持つ仲間が少なく、孤独を感じることが多くなります。
相談できる相手や共に切磋琢磨できる存在が限られることで、精神的な支えを得にくい状況です。
さらに社会的な期待や、支援にも差があります。
男性には「名人を目指せ」「藤井聡太二世になれるかも」といった大きな期待が自然に寄せられますが、女性に対して同様の期待がかけられることは少ない傾向があります。
結果として、進路や将来を考える際に現実的な制約を強く意識せざるを得ません。
こうした構造的な違いが女性の将棋継続率を下げ、プロ棋士を目指す女性の数が少ない要因となっています。
つまり、才能や努力の前段階で、スタートラインに立つ女性の数が圧倒的に少ないという問題が存在しているのです。
脳や身体の差は関係あるのか?
「男性の方が空間認識能力に優れ、将棋に向いているのではないか?」
「女性は言語能力は高いが、将棋のような戦略ゲームには不利ではないか?」
こうした意見は将棋に限らず、理数系分野などでも取り上げられることがあります。
確かに一部の脳科学研究では、平均的に見れば男性は空間把握能力に、女性は言語能力に優れる傾向があるという結果もあります。
しかし、これはあくまで統計上の平均値であり、個人差の方がはるかに大きいことが専門家の共通見解です。
実際、将棋界で活躍する女流棋士の中には、男性顔負けの読みの深さや戦略構築力を持つ人が多数います。
西山朋佳さんのように三段リーグで勝ち越し、あと1勝で四段昇段という実績を残した例もあり、「女性だから将棋に向かない」という考えは明確に否定できます。
また、身体的な事情として、生理やホルモンバランスの変化、妊娠・出産などが集中力や体調に影響する可能性はあります。
しかし、将棋は体力を競うスポーツではなく、理論と経験の積み重ねが重要な競技です。
そのため、身体的な性差が直接勝敗を左右する場面はごくわずかであり、制度やサポート体制を整えれば十分に対応可能です。
要するに脳や身体の違いは、女性がプロ棋士になれない決定的な理由ではありません。
むしろ、制度や心理的要因、競技人口の差といった構造的な問題の方がはるかに大きな壁となっているのです。
女性四段誕生へ向けた改革案
女性がプロ棋士になるための制度は、現状でも形式上は平等です。
奨励会に入会し、三段リーグを突破して四段に昇段すれば、男女問わずプロ棋士として認定されます。
奨励会内では性別による区別はなく、試験や対局条件も同一です。
しかし、これまで女性四段が一人も誕生していない事実を考えると、「制度上は平等でも、実態は平等とは言えない」現状が浮かび上がります。
その背景には、やはり女流棋士制度の存在が影響していると考えられます。
もし、本気で女性プロ棋士を誕生させたいなら、制度改革も検討すべきでしょう。
例えば「奨励会に在籍経験のある女性は、退会後に女流棋士になれない」という規定を設ければ、四段を目指す覚悟がより強固になる可能性があります。
また、制度だけでなく本人の意識改革も欠かせません。
女流という立場に甘んじず、「必ず男性と同じ土俵で戦う」という明確な意志を持つことが必要です。
里見香奈さんや西山朋佳さんのように、三段リーグで挑戦を続けた女性たちは、その覚悟を体現していたと言えるでしょう。
さらに女性奨励会員を取り巻く、環境の改善も急務です。
孤立しがちな状況を防ぐため、心理的なサポートや人的ネットワークを整備することが重要です。
また、社会全体が女性棋士への関心と期待を高めていくことで、将棋界全体の風土も少しずつ変わっていくはずです。
結論:女性四段誕生は可能だ!
女性が将棋で男性に勝てないとされるのは、決して能力そのものが劣っているからではありません。
これまでの歴史の中で、女性が三段リーグで勝ち越し、プロ目前まで迫った例はいくつもありました。
特に西山朋佳さんのように、あと1勝で四段昇段という場面に二度も到達した棋士の存在は、その可能性を明確に示しています。
それでも、いまだに女性プロ棋士が誕生していないのは、制度的な構造や心理的なハードル、競技人口の偏り、さらには将棋界の文化的背景など、複数の要因が複雑に絡み合っているからです。
とりわけ、女流制度という“もう一つのプロ制度”が存在することが、奨励会での必死さを損ない、女性にとって大きな精神的負担となっている点は見逃せません。
しかし、この状況は不変ではありません。
今後の制度改革や意識改革によって、道は大きく変わる可能性があります。
奨励会制度そのものの見直しや、女流制度との関係の整理によって、プロ棋士へのルートがより明確かつ平等に整備されれば、環境は確実に改善されます。
さらに、社会全体が「女性棋士を応援する」雰囲気を育てていくことも重要です。
将棋は体格や体力の差ではなく、知識と経験の積み重ねで勝敗が決まる競技です。
だからこそ、女性がプロ棋士になる日は必ず訪れると信じ、その挑戦を支えていくことが、私たちにできる大切な役割です。
女性プロ棋士の誕生は、ただ実現していないだけで、不可能なことではありません。
その第一歩は、誰かが迷いなく「本気で」四段を目指すことです。
そして、私たち社会全体がその挑戦を温かく見守り、後押しすることが、未来を切り開く原動力になるはずです。

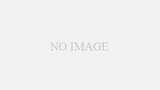
コメント