公務員の仕事は安定していると言われますが、実際には誰にでも向いているわけではありません。
この記事では「公務員に向かない」とされる人の特徴を、5つの視点から詳しく解説します。
パソコン操作の苦手さや要領の悪さなど、努力で改善できる要素は除外しています。
ここでは、性格的にどうしても合いにくいタイプについて、実際の職場の事例を交えながら紹介します。
積み重ね型の努力が報われにくい理由
一見、意外に思われるかもしれませんが、公務員に最も合わないのは、
「地道に努力して着実に力を伸ばしていくタイプ」
です。
たとえば、仕事の習得に時間をかけたい人や、基礎をしっかり固めてから次のステップに進みたい人。
こうした人は決して能力が低いわけではありませんが、公務員の組織構造と噛み合わないことが多いです。
定期異動が成長を妨げる仕組み
公務員の特徴として、数年ごとに必ず人事異動がある点が挙げられます。
努力型の人は、一つの仕事を深く掘り下げようとする傾向がありますよね。
しかし、その頃には異動の時期が訪れます。
ようやく業務を理解して成果を出し始めた矢先に、新しい部署で一から覚え直すことになるのです・・・。
そのたびに、
「自分は仕事が遅い…」
「能力が足りないのでは…?」
と自己否定してしまうこともあります。
評価される前に異動してしまう
器用で柔軟な人は、どんな部署でも早い段階で仕事を覚えられます。
そのため上司からの信頼を得やすく、評価も安定しやすい傾向にあります。
一方で、コツコツ型の人は結果が出るまで時間がかかるため、評価される前に異動してしまうことが少なくありません。
異動先では、また新しい仕事に取り組む必要があり、長い年月をかけても達成感を得づらいのが実情です。
こうした仕組みは、努力を積み重ねて成長していくタイプの人にとって、非常に厳しい環境です。
成果が見え始めるたびに環境が変わり、その努力が報われにくいのです。
過度な期待で評価を失うリスク
異動時には前部署での勤務態度や、印象が次の部署に引き継がれます。
「真面目で頑張る人」という評判が先に伝わると、最初から高い期待をかけられることがあります。
しかし、新しい職場の業務内容がまったく異なる場合、すぐに成果を出すのは難しいものです。
期待とのギャップによって、評価を下げてしまうケースも珍しくありません。
評価が下がると自己肯定感も下がり、「もう頑張っても無駄なのでは…」と感じてしまう人もいます。
公務員の仕事は本来チームで進めるものですが、こうした構造の中で孤独を感じやすくなる人も多いです。
環境変化に順応しにくい人の苦悩
公務員の異動は、3〜4年周期で行われることが一般的です。
地道に積み上げて成果を出すタイプにとっては、この頻繁な環境変化が最も負担になります。
人間関係を一から構築し直し、新しいルールや慣習を覚える必要があるからです。
実際、私自身も5つ目の部署に異動した時点で、将来のビジョンが描けなくなりました。
努力を続けても、また一からやり直し、そして評価はリセットされる・・・。
この繰り返しが続くと「もう限界かもしれない」と、心が折れてしまう人も少なくありません。
地道な努力が好きな人ほど、公務員の仕組みとは噛み合いにくい現実があるのです。
軽く扱われやすい人が抱える壁
2つ目の特徴は、「他人から軽く扱われやすい人」です。
公務員の職場で問題となるのは、市民からの理不尽な対応よりも、内部での人間関係です。
とくに上司からの扱われ方が精神的な負担になることが多く、これが原因で退職を考える人も少なくありません。
信頼関係で不利になりやすい理由
公務員の組織では、若手職員の早期退職が増加しています。
その背景には、業務量の多さだけでなく、人間関係の難しさも大きく関係しています。
軽く見られやすい人は、窓口業務や対外的な場面だけでなく、職場内でも損な立場になりやすいです。
自分の発言が軽く受け流されたり、重要な仕事を任されなかったりといった経験を重ねるうちに、自信を失ってしまう人もいます。
こうしたタイプの人は、早い段階で「自分がどう見られているか?」を意識し、対策を取ることが大切です。
上司からの圧力を受けやすい人の特徴
私自身も入庁当初は、軽んじられやすいタイプでした。
当時の職場では、パワハラまがいの発言や態度を取る上司が少なくなく、毎日がとても苦しい日々。
公務員の世界では、古い価値観を引きずった体質が一部に残っており、それが原因で休職に追い込まれる人もいます。
ただ、私は多くの書籍や経験を通じて、「自分を変える必要はなくても、見せ方は変えられる」と学びました。
他人からどう見えるかを意識し、話し方や表情を少し変えるだけでも、周囲の態度は大きく変わります。
軽く見られやすい人ほど、そのままにしておくと不利な立場を強いられやすいです。
特に公務員のように、年齢層も性格も多様な職場では、「自分をどう見せるか?」が働きやすさを左右します。
軽視されやすい人が取るべき対応策
「自分が軽んじられているか分からない」と感じる人は、それほど深刻に考えなくても大丈夫です。
本当に軽く扱われやすい人は、過去の経験から自覚を持っている場合がほとんどです。
むしろ、自分を客観的に見つめられる人は、対策ができる分だけ安心です。
これまでそうした経験がない人であれば、特に気にする必要はありません。
要は、自分の立場や印象を理解し、必要に応じて行動を変える柔軟さを持つことが重要なのです。
感受性が強い人に重くのしかかる現場
3つ目の特徴は感受性が非常に強く、他人の気持ちや状況に深く共感してしまうタイプの人です。
優しい性格は長所でもありますが、公務員の職場では時にそれが大きなストレスにつながります。
中には「自分は繊細なタイプだ」と話す人もいますが、本当に気をつけるべきなのは、それを言葉にできず抱え込んでしまう人です。
公務員の仕事の中には、どうしても「心のスイッチを切る」必要がある場面があります。
私は過去に、生活保護課へ配属された経験がありますが、そこでは人の生き方や家庭事情と直面することが多くありました。
福祉職の専門採用がない自治体では、事務職員が突然、そうした部署に配属されることもあります。
また、児童福祉の担当になれば、虐待を受けた子どもの写真を見たり、疑いがある家庭に接触したりすることもあります。
中には法律の制約上、親に子どもを返さなければならない場面もあります。
これは職員の怠慢ではなく、法的に職員の判断だけで子を引き離すことができないためです。
現場では、非情に思える判断を迫られることも少なくありません。
こうした経験は、感受性が強い人にとって非常に辛いものになります。
緊急時対応で精神が磨耗する現実
公務員は緊急時や災害時に、業務として動員されることがあります。
たとえば、感染症の拡大期には保健所支援のために、事務職員が派遣されることがあります。
また、大規模地震などが発生した際には、被災地以外の自治体職員が避難所運営のために、1週間前後派遣されることもあります。
このような動員は、どの職種でも例外ではありません。
さらに、鳥インフルエンザなどが発生した際には、殺処分作業の補助として事務職員も現場に入ることがあります。
ニュースで防護服を着て作業している姿の中には、実は一般の事務職員も含まれています。
感染拡大を防ぐためには、誰かがその役割を担わなければなりません。
避けられない任務を担うという宿命
私自身は殺処分業務を経験していませんが、そのマニュアルを読んだだけでも胸が痛くなりました。
業務として割り切れる人もいますが、感受性が強い人にとっては心が追いつかないこともあります。
それでも、公務員という立場上、弱音を吐くことは簡単ではありません。
被害に遭った農家の方の気持ちを考えれば、現場で動くしかないという現実があります。
つまり、公務員には「誰かがやらなければならない仕事」が常に存在します。
そして、その誰かになる可能性は、誰にでもあるのです。
人生のどこで災害や緊急事態が起きるかは、誰にも分かりません。
不運にもその時期に担当部署にいた場合、どんな状況でも職務を全うする覚悟が求められます。
私が勤務していた自治体では、8割以上の職員が「仕事だから仕方ない」と冷静に対応していました。
長く勤めるうちに、そのような心構えが自然と身につくのかもしれません。
しかし、そうした覚悟を持てない人は、どうしても職場に居続けるのが難しくなる傾向があります。
責任ある立場に抵抗を感じる人へ
4つ目の特徴は、人をまとめる立場になることに強い抵抗がある人です。
公務員の職場は、年齢を重ねるにつれて自然と昇進する仕組みが多く、避けようとしても管理職に近い役割を任されることがあります。
たとえ本人にその意志がなくても、組織の流れの中で責任ある立場に就くことが求められるのです。
昇進で増す責任と心理的プレッシャー
公務員は、どんなに慎重な人でも、ある程度の年齢になると係長や、課長補佐といった役職に就く可能性があります。
特に地方自治体では、人事の流れが固定的で、本人の希望にかかわらず昇進が進む傾向があります。
問題は、自分の能力に不安がある場合や、人を指導する立場に抵抗がある場合でも、役職が割り当てられることです。
実際、私が働いていた職場でも、係長になった途端に辞職を選んだ人が何人もいました。
責任が重くなったことで、自分に務まらないと感じてしまうのです。
未経験部署で役職を担う不安
さらに公務員の世界では、初めての部署に配属された段階で、係長として任命されることもあります。
自分が知らない分野でいきなりチームをまとめるのは、相当なプレッシャーです。
私も人前で話すことが苦手で、強いリーダーシップを発揮するタイプではありません。
経験のない部署で係長職を担うことになり、不安と責任の重さに押しつぶされそうになったことを覚えています。
この経験がきっかけで自分の進む道を見直し、結果的に退職を決意しました。
公務員の仕事は実務能力だけでなく、部下の育成や調整力、説明責任など、多くのスキルを求められます。
そのため、リーダーとして人の前に立つことに強い抵抗を持つ人にとっては、次第に苦しく感じられる仕事かもしれません。
業務の意義を見失いやすい人の特徴
最後の特徴は、仕事そのものに意義を見いだせない人です。
特に民間企業や、専門職から転職してきた人に多く見られる傾向で、業務の裁量が少ないことに戸惑う場合があります。
自分の判断で進められる仕事を好む人ほど、もどかしさを感じやすいのが公務員という職業です。
法令順守が求められる厳しい現実
公務員の仕事は、すべて法律や条例に基づいて進められます。
判断の自由度は限られており、「どう思うか?」よりも「どう決まっているか?」が優先されます。
もちろん、現場で工夫できる余地はありますが、最終的な決定は法令に則って行動しなければなりません。
つまり、公務員とは「法律を順守し、制度を正しく運用すること」が最大の使命なのです。
そのため、自分の意見や感情を重視する人にとっては、やりがいを感じにくい場合があります。
自分なりの意義を見つけるために
私が生活保護業務を担当していたときも、「この仕事に意味はあるのか?」と考え込む瞬間がありました。
毎日多くの書類と向き合い、時には制度上の理由で冷たい対応をせざるを得ない場面もあります。
それでも、制度があるからこそ、救われる人が確かにいる。
そのことを理解してから、自分なりのやりがいを見つけられるようになりました。
生活保護制度の存在が、社会から取り残された人を支える最後の砦になっているという事実は、非常に重いものです。
公務員の仕事は、一見すると単調で意味がないように思えることもあります。
しかし、その一つひとつの手続きが社会全体の安定につながっていると考えると、その意義は決して小さくありません。
どの部署に配属されても、自分なりに「誰かの役に立っている」と実感できる視点を持つことが大切です。
まとめ
ここまで紹介した「公務員に向いていない」とされる5つの特徴を整理すると、次のようになります。
・地道に努力を積み重ねるタイプの人
・他人から軽く扱われやすい人
・感受性が強く繊細な性格の人
・リーダー的立場を避けたい人
・公務員の仕事に意義を見いだせない人
ただし、これらの特徴を言い換えれば、どれも誠実さや優しさ、真面目さの表れでもあります。
几帳面で他人の痛みに寄り添える人は、本来、どんな職場にも必要な存在です。
私はすでに退職しましたが、同じような性格の人に「だから辞めるべき」と言うつもりはありません。
むしろ、そうした真面目で思いやりのある人こそ、公務員として働き続けてほしいと感じています。
最近は要領の良さや、口のうまさが評価されやすい傾向がありますが、組織を支えているのは誠実な人たちです。
だからこそ、真面目な人ほど自信を失わないでほしいと思います。
どんな仕事でも、合わない部分は必ずあります。
人間関係に悩んだり、気が進まない仕事をこなすことも避けられません。
しかし、そのような時に「それでも続けてみよう」と思えるかどうかが最も大切です。
たとえ「自分は向いていない」と感じたとしても、公務員として社会に貢献したいという思いがあるなら、諦める必要はありません。
仕事と割り切ってでも努力を続けてみることは、決して無駄にはなりません。
どの職場にも共通して言えることですが、努力を重ねた人ほど、いつか必ずその経験が自分を支えてくれます。

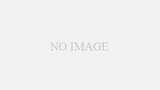
コメント