富士急ハイランドと聞けば、多くの人が思い浮かべるのは数々の絶叫マシンです。
国内外から集まるスリル好きの人々を満足させるため、ここには世界的に見ても類を見ない個性派コースターがそろっています。
その中でも「高飛車(たかびしゃ)」は、特異な落下角度と独創的な演出によって、多くの来場者を驚かせてきた存在です。
最大落下角度121度という驚異的な数値は、登場した2011年当時にギネス世界記録に認定され、世界中から注目を集めました。
ただ真っすぐ落ちるだけでなく、視覚的な恐怖を与える暗闇ドロップや、不意を突くリニアモーター加速。
そして、体を翻弄する多彩な回転エレメントを組み合わせて、他にはない緊張感を生み出しています。
加えて、頂上での静止から一気に突き落とされる121度の大落下は、心理的プレッシャーを極限まで高める要素です。
この記事では、高飛車の基本情報から体験の流れ、他の絶叫マシンとの違いや待ち時間の攻略法まで幅広く解説します。
さらに実際に乗った人の感想や座席ごとの体感の違い、酔いやすい人向けの対策なども盛り込みました。
初めて挑戦する方はもちろん、すでに乗った経験がある方にとっても「なるほど」と思える情報を詰め込みましたので、最後まで楽しんで読んでいただければと思います。
高飛車とはどんなコースター?
高飛車は2011年7月16日にオープンした、富士急ハイランドを代表する大型ローラーコースターです。
製造はドイツの遊具メーカー「Gerstlauer Amusement Rides社」によるもので、同社が開発した「ユーロファイター1000」というモデルがベースになっています。
車両はコンパクトな8人乗り編成で、狭い車体だからこそスピード感や揺れが、体に直接伝わりやすく、恐怖感が増幅されます。
にもかかわらず、全長1,000mを超える広大なレイアウトを走り抜ける設計がなされており、小さな編成に大スケールを詰め込んだ異色の存在です。
【基本データ】
コース全長:1004m
高さ:43m
最大落下角度:121度
最高速度:100km/h
最大加速度:4.4G
所要時間:約2分30秒〜2分50秒
乗車定員:8名(4名×2列)
身長制限:125cm以上
年齢制限:64歳まで
安全装置には、肩からしっかり体をホールドするオーバーヘッドハーネスを採用し、スリルを保ちつつも安全性を確保しています。
小型編成のため座席ごとの体感差は少なめですが、前列は視界が開けてスリルが増し、後列は揺れが抑えられて比較的安心感があると言われています。
高飛車は「FUJIYAMA」「ええじゃないか」「ド・ドドンパ(現在は営業終了)」と並び、富士急“四大コースター”に数えられる存在です。
他の3機種がスピードや浮遊感を前面に出しているのに対し、高飛車は「心理的スリル」「視覚的恐怖」といった要素に特化しているのが大きな特徴です。
ライドの流れと絶叫シーンを解説
暗闇の中で体が浮く予測不能の落下
スタート直後、高飛車は暗闇のトンネルへと滑り込むように進んでいきます。
外の景色が一切見えなくなり、乗客の視界は完全に遮断されます。
その直後に突然訪れるのが、心臓を突き落とすような急落下です。
通常のコースターであれば外からレールの動きが見え、「そろそろ落ちるな」と予測することができます。
しかし、高飛車では視覚情報が奪われているため、心の準備ができないまま一気に下へ叩き落とされるのです。
この仕掛けは「高飛車最大の衝撃ポイント」といわれ、初めて挑戦する人だけでなく、複数回体験したことがある人ですら、思わず悲鳴をあげてしまうほどです。
暗闇の中で一瞬体がふわっと浮く感覚と、予測不能の落下は強烈な印象を残し、その後の展開への緊張感を一気に高めていきます。
ド・ドドンパに匹敵する急加速
暗闇のトンネルを抜けようとした瞬間、速度が落ち着くと思ったのも束の間、突如リニアモーターが作動します。
そしてわずか2秒ほどで、時速100kmまで一気に加速するのです。
小型車両のため、体感速度はより鋭く、シートに全身が押し付けられるほどの加速Gが乗客を襲います。
この瞬間を「かつて存在したド・ドドンパを思い出す」と表現する人も多いほどで、短い時間ながらインパクトは絶大です。
さらに、暗闇から突然光の世界へと飛び出す演出が加わり、視覚的にも強い衝撃を与えます。
音を切り裂くような風圧と同時に加速する感覚は、多くの人にとって忘れられない体験となります。
全部で7か所もある回転要素
屋外に飛び出した車両は、そのまま回転エレメントの連続区間へ突入します。
高飛車には、全部で7か所もの回転要素が盛り込まれており、インメルマンやコークスクリュー、ハートラインロール、ダイブ・ループなどが巧みに組み合わされています。
注目すべきは、それぞれの回転が単調に繰り返されるのではなく、異なる方向から次々と仕掛けられる点です。
「次はどちらに回るのか」という緊張が途切れないまま走行が続き、乗客の集中力を奪っていきます。
この区間では浮遊感よりも、体がねじれるような強い遠心力や圧迫感を受けやすく、人によっては目が回りやすくなります。
特に連続する回転後半は首への負担が大きくなるため、頭をしっかりとヘッドレストに預けておくことが、安全に楽しむための重要なポイントです。
頂点で停止する最恐ポイント
激しい回転を抜けると、今度は車両が垂直に近い角度で空へと巻き上げられていきます。
真上を見上げながら壁を登るような体勢となり、次第に背中が地面を向く不安定な感覚に襲われます。
そして高さ43mの頂点に到達すると、車両は一旦その場に静止。
乗客の目の前には真下へと落ちる断崖絶壁が広がり、足元には何もない状況になります。
ただ「落ちる瞬間」を待つしかない時間が続くのです。
この停止の演出は「高飛車の最恐ポイント」と言われ、落下そのもの以上に強烈な心理的プレッシャーを与えます。
人によっては、この数秒間が一番長く感じられ、心臓を鷲掴みにされるような緊張を味わうことになります。
空中に放り出される様な落下
そしてついに訪れるクライマックス、最大の見せ場が121度の大落下です。
ゆっくりと前へ進み出した瞬間、視界の先にはレールがなく、まるで空中に放り出されるようにえぐり込む落下が始まります。
通常の90度垂直落下を超える設計は、他のどのコースターでも味わえない独特の体験です。
「落ちる」というより「前方に吸い込まれる」感覚が強く、視覚的な恐怖と圧倒的な速度感が一気に襲いかかります。
意外にも浮遊感は少なめで、むしろ速度と重力の圧力を強烈に感じるのが特徴です。
そのため浮遊感が苦手な人でも挑戦しやすい一方で、静止から解放された瞬間の衝撃は大きく、思わず叫び声をあげてしまう人が後を絶ちません。
高飛車が怖いと言われる理由は何か?
視覚の恐怖と精神的プレッシャー
高飛車の最大の恐怖は、単なる「落ちる感覚」ではなく、視覚的なインパクトと心理的な圧迫感にあります。
特に121度の大落下では、頂上で静止させられることで視界に広がるのは、真下の断崖絶壁。
通常のコースターは、登り切った瞬間にすぐ落下することが多いです。
しかし、高飛車はあえて停止させることで「まだか…まだか…」と乗客に緊張を強いるのです。
これにより落下そのものよりも、落ちる直前に待たされる時間が最も怖いと感じる人が多くなります。
実際に落下が始まれば一瞬で終わるのですが、停止中の数秒間がやたらと長く感じられ、強烈に記憶へ刻まれます。
「待たされる恐怖」を演出として活用している点が、高飛車を特別な存在にしているのです。
浮遊感よりも加速と圧迫感が強い
一方で、高飛車は「浮遊感」を強く味わえるコースターではありません。
例えばFUJIYAMAは、70m級の大落差でふわっと浮く感覚を長く楽しめますし、ええじゃないかは座席が回転するため、何度も無重力状態を体験できます。
それに対して高飛車では、回転エレメントや落下の一瞬で短い浮遊感を感じられる程度で、全体的には強い加速や遠心力、視覚的な恐怖のほうが前面に出ています。
このため「浮遊感が苦手だから怖い」という人にとっては挑戦しやすい一方で、「回転が多く酔いやすい」と感じる人も少なくありません。
つまり、高飛車の怖さは「体が浮くスリル」ではなく、「視覚と心理で追い詰められるスリル」によって生み出されているのです。
高飛車に乗った人の体験談と感想
高飛車に実際に体験した人の口コミを見ても、共通して語られるのは「浮遊感よりも心理的な怖さが強い」という点です。
「121度の落下を見た瞬間に心が折れそうになったけど、思ったよりふわっと感が少なくて大丈夫だった」
「落下そのものより、止まって下を見せつけられるあの時間が一番怖い」
「暗闇でのドロップやリニア加速が強烈で、頭がついていかないまま終わった」
「浮遊感は弱いけど、見せ方がうますぎて心理的に追い込まれる」
このように高飛車は、体験者の多くが「演出の恐怖」に圧倒されていることが分かります。
結果として、浮遊感が苦手な初心者から、スリルを求める上級者まで幅広く受け入れられるアトラクションになっているのです。
他の4大コースターと比べてどうなのか?
FUJIYAMA
“キング・オブ・コースター”と呼ばれるFUJIYAMAは、富士急の代名詞ともいえる存在です。
全長2,045mという圧倒的なスケールを誇り、最大落差70mの大落下では空を飛んでいるような浮遊感を長時間味わえます。
さらに、富士山の雄大な景色を眺めながら走行できる爽快感も特徴で、絶叫マシンの醍醐味を存分に体験できる王道のコースターです。
「浮遊感を味わいたいならまずFUJIYAMA」と言われるほどの存在感があります。
ええじゃないか
座席が前後左右に回転する世界的にも珍しい「4次元コースター」。
レール自体のねじれに加え、座席の回転が加わることで上下左右の感覚が完全に失われます。
強烈な浮遊感や無重力状態を何度も体験でき、乗客は自分がどちらに向いているのか分からなくなるほど混乱させられます。
「何が起きているのか分からないまま終わった」と語る人が多いほどの恐怖度で、富士急の中でも特に「日本一怖い」と言われやすいコースターです。
ド・ドドンパ(営業終了)
惜しまれつつ営業を終了した、伝説のコースター「ド・ドドンパ」。
最大の魅力はスタート直後の爆発的な加速で、わずか1.56秒で時速180kmに到達する発進は、世界中のコースターの中でも屈指の衝撃でした。
浮遊感自体は少なかったものの、強烈な加速Gと巨大ループの迫力で恐怖を生み出しており、体験した人にとって忘れられない存在です。
現在は運行していませんが、今なお富士急の歴史の中で語り継がれる存在となっています。
高飛車
そして高飛車は、これらのコースターとは異なるベクトルで恐怖を追求しています。
暗闇でのドロップやリニア加速、頂上での停止からの121度落下といった「演出による心理的スリル」が主役です。
浮遊感は比較的控えめで、初心者でも挑戦しやすい一方、「待たされる恐怖」のインパクトは絶大です。
短い時間にさまざまな要素を凝縮しており、「ジェットコースターのエッセンスを詰め込んだ一台」といえるでしょう。
高飛車の待ち時間はどれぐらい?
高飛車は園内の中央にそびえ立ち、ひときわ目立つ存在であるため、常に多くの人が行列を作ります。
そのため、待ち時間は短い時でも50分前後、通常の平日であれば60〜90分程度は見込む必要があります。
特に土日祝日や大型連休、夏休みやお盆などの繁忙期には、2時間を超える待ち時間になることも珍しくありません。
昼前後から午後にかけては混雑のピークを迎えるため、できるだけ効率良く体験したい人は開園直後を狙うのが最も確実です。
また、富士急ハイランドには「絶叫優先券」という、有料チケットが用意されています。
これを活用すれば、人気アトラクションの長い行列を回避して、短い待ち時間で体験することが可能です。
オンラインの事前購入が可能で、当日は売り切れることも多いため、確実に乗りたい場合は早めに準備しておくと安心です。
さらに天候や気温、運行状況によって待ち時間が変動する場合もあります。
雨天や強風時には運行が一時停止になることがあり、その後、再開した際には待ち時間が急激に伸びることもあります。
公式アプリや園内掲示板で、リアルタイムの運行情報を確認しながら行動すると効率よく楽しめます。
前列と後列での恐怖感の違い
高飛車は1両8人乗りの小型編成で、前後2列の車両がレールを疾走する仕組みです。
座席の位置による体感の差は大きくないと言われていますが、実際には前列と後列で感じ方に違いがあります。
前列は景色も恐怖もダイレクト体験
前列に座ると、視界を遮るものが一切なく、暗闇のトンネルから外へ飛び出す瞬間や、121度の大落下で真下を見下ろす光景がダイレクトに伝わります。
「足元にレールが見えない」という演出効果も相まって、恐怖度は格段に上昇します。
スリルを存分に味わいたい人や、迫力ある景色を楽しみたい人には前列が特におすすめです。
後列は落下の迫力がやや緩和される
後列は前の座席に視界が遮られる分、落下の直前の光景がやや緩和されます。
そのため視覚的な恐怖は軽減され、全体的に落ち着いた体験になると感じる人も多いです。
また振動も比較的抑えられているため、体への負担が軽く「少し怖さを和らげたい」という人には向いています。
中央寄りは安心感がある
一方で、横の座席に人が並ぶ中央寄りのポジションは、外側よりも圧迫感が少なく、安心して座れるという声があります。
家族や友人と一緒に乗る場合には、絶叫が好きな人を前列に、少し怖さを避けたい人を後列や中央に座らせると、それぞれが自分に合った楽しみ方をしやすくなります。
座席選びひとつでも体験の印象は大きく変わるため、挑戦する際には目的や好みに応じて選ぶのがおすすめです。
高飛車で酔わないための工夫と予防法
高飛車は浮遊感が控えめな分、回転や加速による負荷が大きく、酔いやすいと感じる人も少なくありません。
特に三半規管が弱い人にとっては、ええじゃないか以上に「回転で目が回る」と言う声もあるほどです。
安心して楽しむためには、あらかじめいくつかの対策をしておくことが効果的です。
ヘッドレストで首の負担を減らす
高飛車は合計7か所に回転エレメントがあり、走行中は首や頭が振られやすい構造になっています。
そのため、頭をヘッドレストにしっかり固定することが、酔いや不快感を防ぐ第一歩です。
背中と頭をシートに密着させておけば、急な揺れが直接伝わりにくくなり、めまいや首の疲れを軽減できます。
ただし、力を入れすぎると逆に疲れてしまうため、リラックスしながら「預ける」イメージで体を固定するのがコツです。
動きを先読みして体を順応させる
走行中は、視線を安定させることも重要です。
コースの先を見てレールの動きを追うようにすると、次に来る回転や落下に体が順応しやすくなります。
反対に、周囲をキョロキョロしていると平衡感覚が乱れ、酔いやすくなります。
暗闇の区間ではレールが見えないこともありますが、光の差し込みや進行方向を意識するだけでも大きな違いがあります。
特に回転が連続する場面では「次に体がどう動くのか」を意識しておくと、予想外の揺れに翻弄されにくくなります。
食事の時間や内容を工夫する
乗車前の食事内容や、タイミングも酔いやすさに直結します。
空腹のままでは血糖値が下がり、めまいや吐き気を感じやすくなりますし、満腹状態では胃が圧迫されて不快感を覚える可能性が高まります。
高飛車に挑戦する場合は、直前に食べ過ぎないように注意し、できれば2時間ほど前に軽食を済ませるのが理想です。
消化にやさしい炭水化物やバナナなどを選ぶと安心で、揚げ物など油っぽい食事や炭酸飲料は避けるのが無難です。
必要に応じて酔い止めを服用する
どうしても酔いが心配な場合は、事前に酔い止めを服用するのもおすすめです。
市販薬の中には眠気を抑えたタイプもあるため、遊園地で一日を楽しむ予定がある人にも使いやすいでしょう。
効果を安定させるためには出発直前ではなく、乗車30分〜1時間前に服用するのが望ましいとされています。
また薬を使わない場合でも、ミント系のガムやハッカ飴などを口に含むことで気分がリフレッシュし、乗り物酔いの不快感を和らげやすくなります。
これらの対策を意識しておけば、酔いやすい体質の人でも不安を減らし、安心して高飛車を楽しむことができます。
高飛車の特徴と楽しみ方を総まとめ
目で感じる迫力と心を追い込む緊張感
高飛車の大きな特徴は、121度という異次元の落下角度にあります。
数値としても驚異的ですが、それ以上に頂上で一旦停止させられた後に真下を見下ろす時間が、恐怖心を一気に増幅させます。
「落ちる瞬間」そのものよりも、「いつ落ちるのか分からない時間」の方が強烈で、心臓を締めつけられるような緊張を味わえるのが、高飛車ならではです。
また、スタート直後の暗闇ドロップやリニアモーターによる急加速、不意打ちの演出が随所に散りばめられており、最後まで気を抜けません。
浮遊感が少なく初心者でも乗りやすい
FUJIYAMAやええじゃないかのように、大きくふわっと浮き上がる感覚は高飛車にはほとんどありません。
その代わりに、強い加速や遠心力、回転による圧迫感が中心となっており、「浮遊感が苦手だから絶叫マシンに乗れない」という人にも比較的挑戦しやすい存在です。
ただし、回転要素が多いため「目が回る」「酔いやすい」と感じる人もいます。
浮遊感が少なくとも、違う種類の負荷が強烈にかかるため、別の意味でスリルを味わえるコースターです。
絶叫マシンの要素を凝縮したバランス設計
高飛車は、暗闇ドロップ、リニア加速、複数の回転、垂直上昇、121度落下と、絶叫コースターの要素を短時間に詰め込んでいます。
「ジェットコースターの醍醐味を凝縮した一台」
といえる構成で、絶叫マシンにある程度慣れてきた人の次のステップとしても最適です。
口コミでも、
「FUJIYAMAやええじゃないかのような圧倒的浮遊感はないけれど、心理的な怖さは高飛車が一番だった」
と語る人が多く、他の三大コースターと比べても独自の立ち位置を築いています。

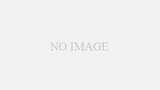
コメント