「正月飾りを片付けるのを忘れてしまった」と気づき、どうすれば良いのか迷ったことはありませんか?
年末年始は慌ただしく過ごすことが多く、気が付けば飾りが残ったままという状況も珍しくありません。
ただ、正月飾りには神聖な意味合いがあるため、できるだけ丁寧に処理したいと考える方も多いはずです。
地域ごとに風習や片付けの時期が異なると、どの方法が正しいのか判断に困ることもあります。
この記事では、自宅でできる処理の流れから、神社に持ち込む場合の方法まで、正月飾りの片付け方を詳しく解説。
今からでも取り入れられる実践的な方法を知って、安心して正月飾りを整理していきましょう。
松の内が終わったら片付けるのが基本
正月飾りを外す時期は、地域やしきたりによって違いますが、一般的には「松の内」が終わる日が目安とされています。
松の内とは、歳神様が正月飾りを目印に家を訪れる期間のことで、関東では1月7日、関西では1月15日までとされています。
一方で、地域によっては「二十日正月」と呼ばれる、1月20日まで飾る習慣も残っています。
そのため、最も確実なのは、住んでいる地域の風習や周囲の家庭の様子を確認し、時期を合わせて片付けることです。
正月飾りは歳神様を迎える目印
松の内は、新しい年に歳神様を迎え入れるための、大切な期間とされています。
正月飾りはその目印として飾られ、家に福を呼び込む準備を整える役割を果たします。
松の内が過ぎると飾りの役目は終わるため、外して処分するのが習わしです。
関東では七草粥をいただく1月7日、関西では小正月にあたる1月15日が、片付けの基準となることが多いです。
地域によって片付けの時期は異なる
正月飾りを外す日は、地域によって大きな違いがあります。

そのため、片付けのタイミングに迷った場合は、まずは近所の家庭の様子を参考にするのが安心です。
また、引っ越しなどで土地の風習がわからないときには、事前に地域の伝統を調べておくと失敗を防げます。
松の内を過ぎた後の片付け方法
もし、松の内が終わっても片付けを忘れてしまった場合でも、慌てる必要はありません。
正月飾りはすでに歳神様を迎える役割を果たしているため、遅れて処分しても失礼にはあたらないからです。
大切なのは、外す際に感謝の気持ちを込めて丁寧に扱うことです。
この記事で紹介する方法を実践すれば、今からでもきちんと整理できます。
正月飾りを片付ける際には、次の点を意識すると安心です。
・地域の伝統に従って時期を選ぶこと。
・近隣の家庭の様子を参考にすること。
・時期を過ぎても気にせず感謝を込めて片付けること。
感謝を込めて丁寧に処分する
正月飾りを片付ける日は、基本的に松の内の終了日が基準となります。
ただし、地域や生活の都合によって前後することもあるため、柔軟に考えることも大切です。
最も重視したいのは、歳神様を迎えられたことへの感謝の気持ちです。
気持ちを込めて片付けることで、新しい年を心地よく始められます。
家庭ごみとしてそのまま捨てない
自宅で正月飾りを処分する場合、注意が必要です。
正月飾りは神聖な意味を持つものなので、ほかの家庭ごみと一緒に捨てるのは適切ではありません。
処分する際は正しい手順を守り、神聖さを取り除いたうえで処理することが大切です。
以下に、自宅で安全に片付けるための方法を紹介します。
まずは塩で全体を清める
処分の前に、まず飾りを塩で清めましょう。
これは飾りが持つ神聖な力を和らげ、安心して片付けられるようにするための大切な儀式です。
準備として、清潔な白い紙や新聞紙を広げ、その上に飾りを置きます。
白い紙は神聖さを表すため、可能なら白紙を用意すると良いでしょう。
清めるときは、左・右・中央の順に軽く塩を振ります。
分量は、ひとつまみ程度で十分です。
意味に厳密な決まりはありませんが、全体に均等に振ることを意識してください。
最後に「これまでありがとうございました」と感謝を込めて手を合わせれば、より丁寧な処分となります。
包んで分別してから処理する
お清めが終わったら、自治体のルールに従ってごみに出せるよう準備をします。
まずは、紙や布で丁寧に包みます。
新聞紙などでも構いませんが、きれいに整えて包むことを心がけましょう。
次に、飾りについている装飾品を確認します。
プラスチック製のリボンや金属の針金などは取り外し、素材ごとに分別します。
プラスチック部分は「不燃ごみ」、燃える素材は「可燃ごみ」として処理します。
門松のような大型の飾りは、自治体によっては粗大ごみに分類される場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
処分時の注意点と心得
自宅で処分する際は、以下の点に気を付けましょう。
・プラスチックや金属は、必ず取り外して分別すること。
・門松などの大きな飾りは、粗大ごみになることがあるため注意すること。
・自治体ごとの収集日や、分別方法を確認すること。
・環境への配慮を忘れず、適切な方法で処理すること。
値段に関係なく清めるのが基本
正月飾りは高価なものでも、100円ショップの飾りや手作りのものでも、すべて神聖な意味を持つと考えられます。
値段は関係ありません。
そのため、必ずお清めをしてから処分することが望ましいです。
もし、自宅での処理に不安を感じる場合は、神社のお焚き上げに持ち込むのも安心できる方法です。
少し手間はかかりますが、こうした手順を踏むことで心穏やかに片付けができます。
新しい年を清々しい気持ちで迎えるためにも、丁寧に対応しましょう。
しめ縄は神社で処分できる
しめ縄やそのほかの正月飾りは、地元の神社に持ち込んで処理してもらうことができます。
多くの神社では、1月15日頃を中心に「どんど焼き」や「お焚き上げ」といった行事を行い、飾りを清めながら焼却します。
持ち込む際は飾りを紙で丁寧に包み、プラスチックや金属などの燃えない素材が、混ざっていないかを確認しておくと安心です。
ただし地域によっては、どんど焼きを実施していない神社もあるため、事前に開催の有無や日程を調べておきましょう。
また、松の内を過ぎても「古札納所」で受け付けている神社もあり、時期を逃してしまった場合でも相談できる場合があります。
さらに、お焚き上げを依頼する際には、数百円程度のお金が必要になることもあるため、あらかじめ小銭を用意しておくと手続きがスムーズです。
こうした方法を活用すれば、神聖な飾りを安心して処分できます。
外し忘れても縁起は悪くない
正月飾りを片付けるのをうっかり忘れてしまっても、正しい手順で対応すれば心配はいりません。
気づいた時点で飾りを外し、これまで紹介した方法で処理を行えば問題はありません。
たとえ、どんど焼きやお焚き上げの時期を逃してしまった場合でも、塩で清めてから自治体の分別ルールに従って家庭ごみとして処分できます。
「遅れて外すと縁起が悪いのでは」と不安に思う人もいますが、根拠のあるものではありません。
大切なのは、心を込めて丁寧に片付ける姿勢です。
飾ったまま放置するのは良くない
ただし、長い間飾ったままにしておくと見映えが悪くなり、周囲からだらしない印象を持たれることがあります。
そのため忘れていたと気づいたら、できるだけ早めに外すことをおすすめします。
感謝の気持ちを込めて片付ければ、遅れて処分しても新しい年を気持ちよく迎えることができます。
「一夜飾り」は避けた方が良い
正月飾りは新年に歳神様を迎え、家族の無病息災や繁栄を願うために飾られるものです。
そのため、松の内の間に準備して飾るのが望ましいとされています。
ただし、地域によって期間には差があるため、土地の風習に従うことが基本です。
特に避けたいのは、12月31日に飾る「一夜飾り」と呼ばれるものです。
これは歳神様を迎える準備が不十分だとされ、縁起が悪いと考えられています。
また、片付けが1月20日以降にまでずれ込むと、歳神様への礼を欠くとされる場合があります。
こうした点を意識して、計画的に飾りと片付けを行うことが大切です。
12月28日までに準備しておく
正月飾りを買うのは、12月中旬以降が一般的です。
新しい年を迎える準備として、この時期から徐々に用意する人が多いでしょう。
ただし、購入を避けた方が良い日もあります。
12月29日は「二重苦」を連想させる語呂から縁起が悪いとされ、12月31日の「一夜飾り」も好ましくありません。
そのため最も適しているのは、12月28日までに用意を整えることです。
早めに準備すれば選択肢も多く、落ち着いて新年を迎えられます。
毎年新しい飾りを用意する
正月飾りは基本的に、毎年新しくするのが良いとされています。
その年の歳神様を新鮮な気持ちで迎えるという、日本の伝統に基づいた習わしです。
新しい飾りを用意することで、神聖さを保ちながら新年を迎えられると考えられています。
ただし、デザイン性の高いインテリア用の飾りを、再利用するのは問題ありません。
室内の雰囲気を彩るアイテムとして、長く使うことができます。
再利用する場合は、カビや汚れがつかないように清潔な場所で保管しておくことが大切です。
湿気の少ない環境に収納し、翌年も気持ちよく飾れるようにしましょう。
まとめ
正月飾りを片付ける時期は、地域の習慣に従って、松の内が終わる頃を目安にするのが一般的です。
関東では1月7日、関西では1月15日とされていますが、地域や家庭によって伝統が異なるため、確認してそれに合わせることが大切です。
新年の準備に関しては、12月31日の「一夜飾り」は縁起が悪いとされているため避け、12月28日までに整えておくのが望ましいとされています。
処分の際には、まず塩で清め、紙に包んでから自治体の分別ルールに従ってごみに出すのが基本です。
門松のように大きな飾りは粗大ごみ扱いとなる場合もあるため、事前に自治体へ確認しておくと安心です。
また、神社で行われる「どんど焼き」や「お焚き上げ」に持ち込む方法も広く行われており、特に1月15日前後に実施されることが多く、しめ縄などほかの飾りも一緒に浄化して処理してもらえます。
家庭で処分する場合は、燃えるものと燃えないものをしっかり分け、収集日に合わせて出すようにしましょう。
正月飾りは本来、毎年新調するのが理想とされていますが、環境面や実用性を考えて再利用するという選択肢もあります。
いずれにしても、飾りは神聖なものとして、感謝の気持ちを込めて取り扱うことが大切です。
もし、片付けを忘れてしまったとしても、気づいた時点で丁寧に処理すれば問題はありません。
感謝の心をもって正しく片付けることで、清々しい気持ちで新しい一年を迎えることができるでしょう。

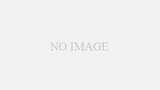
コメント