理系の進路の一つとして注目されることのあるのが、技術系公務員です。
しかし、多くの学生は民間企業を志望するため、技術職の公務員に関する情報はあまり多くありません。
公務員試験を調べても、行政職を前提とした内容ばかりで、技術職について詳しく解説しているものは少ないのが実情です。
自分が希望する職種の情報が乏しく、「もっと詳しく知りたい」と感じている人も多いでしょう。
そこで今回は、技術系公務員の仕事内容や職場環境について紹介します。
この記事を読めば、技術職の働き方が具体的にイメージでき、不安が和らぐきっかけになります。
公務員の技術職の種類
自治体ごとに名称が異なる
「技術職」といっても、その中には多様な専門分野があります。
国や地方自治体で採用されている技術系職員には、土木職、建築職、化学職、物理職、電気・電子・デジタル職、機械職、獣医職、薬剤職、農学職、造園職、農業土木職、林学職、水産職などが含まれます。
ただし、これらの呼称は自治体や国の機関によって、少しずつ異なる場合があります。
特に土木職は、多くの自治体で広く募集されていますが、農業土木や林学のような分野では「若干名」といった形で採用枠が少ないことも珍しくありません。
採用がない自治体も存在する
また、技術系ならではの特徴として、特定の職種自体を募集していない自治体もあります。
マイナーな分野では、ある年には採用があっても翌年には行われないというケースも見られます。
そのため、自分の希望する職種が採用対象になっているかどうかは、早めに確認しておくことが大切です。
多くの自治体では、過去の採用試験結果がホームページに掲載されています。
募集人数の推移を確認すれば、志望職種の採用状況を把握するのに役立ちます。
技術職が必ずしもホワイトとは限らない
行政職より技術職の方が働きやすい、とよく言われます。
「技術系はホワイト」といったイメージも広がっていますが、必ずしもそうとは限りません。
では、なぜ技術系公務員はホワイトとされることがあるのでしょうか?
実際のメリットとデメリットを整理しながら、説明していきます。
激務部署に配属されにくい
技術職が比較的働きやすいとされる理由の一つは、財務や人事のような多忙な部署に配属される可能性が低い点です。
技術職は専門分野ごとの配属が基本で、範囲がある程度限定されています。
たとえば農業職であれば、農業や産業関連の部署にほぼ絞られます。
一方、行政職の場合は財務や人事といった激務部署に配属されることもあるため、技術職の方が負担が軽いという印象を持たれるのです。
服務ルールが緩やかな傾向
技術系の職場では、服務規程がやや柔軟に運用される場合があります。
一例として、本来は事前に必要な休暇申請を、後から提出しても大きな問題にならないなど、行政職に比べてルールが緩めに扱われることもあります。
実際に、私が技術系の部署で勤務していた際には、特に不自然さを感じませんでしたが、行政職が多い部署へ異動すると「これまでの環境は緩かった」と気づくこともありました。
閉鎖的な雰囲気になりやすい
ただし、配属先が技術系のみで構成される場合、職場が閉鎖的になることもあります。
そのような環境では、コンプライアンス意識が低かったり、ルールの徹底が不十分な場合も見受けられます。
行政職の職員から「技術職は甘い」と評価されるのは、こうした背景によるものです。
ブラックな一面もある
一方で、技術職だからといって、すべてが快適というわけではありません。
代表的な課題としては、以下のような点が挙げられます。
・技術系でも激務部署が存在する
・体育会系の文化が残っている
・男性中心の職場環境が強い
・セクハラを受けやすいケースがある
・異動直後でも即戦力として期待される
これらは、技術職として働いた経験がある人であれば、多くが共感する内容でしょう。
中枢部署では残業も多い
技術系の部署でも、激務となる職場は確かに存在します。
特に国の機関や自治体の本庁のような中枢では、優秀な技術職員が深夜まで働いていることもあります。
「技術職は残業が少ない」というイメージを持たれることがありますが、実際には部署次第で行政職と同じくらい忙しい場合もあります。
残業の多さは配属先によって変わるため、行政職と大きな違いはないとも言えるでしょう。
男性社会で昭和的な雰囲気が残る
技術系の職場では、今も体育会系の風土や男性中心の雰囲気が、根強く残っている場合があります。
女性職員の数は増えてきていますが、関係団体や取引先が男性中心であることも多く、昭和の部活動を思わせる空気が漂うこともあります。
そのため、厳しい上下関係や理不尽な言動に抵抗を感じる人は、職場を「ブラック」と感じることも少なくありません。
技術職が、必ずしも快適な職場とは限らない点は、あらかじめ理解しておく必要があります。
セクハラのリスクがある
女性職員が増えてきているとはいえ、依然として男性が多数を占める職場が多いです。
そのため、女性がセクハラを受ける可能性がある点は大きな懸念です。
特に顕著なのは、同僚ではなく外部団体の担当者などからの言動で、飲み会などでは注意が必要な場面もあります。
嫌な経験をする人も少なくないため、この点は課題として意識しておくべきでしょう。
異動直後から大きな期待を受ける
もう一つの大きな負担は、異動して間もない時期から「専門家」として期待されることです。
行政職でも似た傾向はありますが、技術職ではその傾向がより強く表れます。
通常は3年ほどで異動がありますが、異動先はまったく別の分野であることも珍しくありません。
それにもかかわらず、初日から高度な専門対応を求められる場合もあり、慣れるまでは強いプレッシャーを感じやすいです。
無理に理解したふりをして業務を進め、後から問題に発展するケースも少なくありません。
まとめ
技術系公務員といっても、土木や建築、機械、農業などさまざまな専門分野があり、職種ごとに求められる役割も異なります。
世間では「技術職=ホワイト」という印象を持たれることもありますが、すべての職場がそうとは限りません。
メリットとしては、財務や人事といった激務部署に配属されにくいことや、服務規程が柔軟に運用される職場が多いことが挙げられます。
また、異動希望が比較的通りやすい傾向があるのも魅力です。
一方で、セクハラのリスクがあったり、異動直後から専門家としての働きを求められるなど、厳しい一面も存在します。
体育会系の文化や男性中心の雰囲気が残る職場では、負担を感じやすい人も少なくありません。
理系出身者には、公務員のほかにも数多くの進路が用意されています。
後悔しない進路選択をするためには、こうした実情を理解し、十分な情報を集めた上で判断することが大切です。

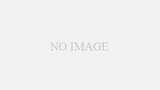
コメント