公務員は安定性の高さで、広く知られている職業です。
さらに、休暇制度がしっかり整っているイメージを持つ人も、多いのではないでしょうか。
安定した働き方や休暇の取りやすさに魅力を感じて、公務員を目指す人も少なくありません。
実際に働いてみると、安定した収入や労働環境、そして休暇制度の充実度は本物だと実感します。
安定を求める人には男女問わずおすすめできますが、特に女性にとっては強くすすめたい仕事です。
安定した働き方を考えている女性は、ぜひ最後まで読んでみてください。
抜群の安定感で将来も安心できる仕事
安定を重視したい女性にとって、公務員という働き方は大きな魅力があります。
たとえば、
「○歳までに結婚したい」
「○歳までに子どもを育てたい」
といった人生設計を立てやすい点は、とても大きな強みです。
公務員が将来を見据えやすい理由には、次の3つが挙げられます。
1.給与が年齢に応じて少しずつ上がる
2.解雇のリスクがほとんどない
3.住宅ローンが通りやすい
それぞれのポイントについて、詳しく説明していきます。
収入の見通しを立てやすい職業
公務員の給与は、年齢に応じて段階的に上がっていく仕組みです。
「年功序列」という言葉を、耳にしたことがある人も多いでしょう。
勤務年数を重ねていけば、大きな問題がない限り役職や給与が少しずつ上昇していきます。
同年代の職員は、おおむね同じような立場と給与水準にあり、将来的な収入の見通しが立てやすいのが特徴です。
そのため「数年後に車を買い替える」「○歳までに家を購入する」といったライフプランも安心して計画できます。
このように収入の予測がしやすい点は、公務員ならではの魅力といえます。
終身雇用を前提とした安心感
公務員は基本的に、解雇の心配がありません。
もちろん、不正や犯罪行為をすれば処分される可能性はありますが、通常通りに勤務していれば問題なく働き続けられます。
たとえ業務で失敗したり、上司と意見が合わなかったとしても、それだけで職を失うことはありません。
民間企業の中にも安定した職場はありますが、公務員は特に「定年まで雇用が保障される」という特徴があります。
安定した収入が見込めることで、将来の計画を立てやすい大きな要因となっています。
ローン審査に強く金利も優遇されやすい
マイホームの購入を検討している人にとって、公務員の社会的信用は大きなメリットになります。
「安定した収入が見込める職業」とされているため、金融機関の住宅ローン審査に通りやすい傾向があります。
さらに借入条件としての金利が、優遇されるケースも少なくありません。
「公務員」という立場そのものが信頼につながるため、住宅購入を考えている人にとっては心強い要素になります。
有給で利用できる休暇制度が豊富にある
公務員を女性にすすめたい理由のひとつに、休暇制度の充実があります。
女性にとってありがたい休暇が数多く整備されており、どれも有給として扱われるため給与は全額支給されます。
ここでは代表的な制度を中心に取り上げますが、実際にはさらに多くの制度が用意されています。
利用されやすい休暇をいくつか紹介していきます。
生理休暇
体調が思わしくないときに活用できるのが、生理休暇です。
1回の生理ごとに2〜3日取得でき、日数は自治体によって異なります。
名前の影響から利用率は低めですが、最近では呼び名を変えたり、時間単位で使えるようにするなど改善が進んでいます。
以前よりも使いやすい制度へと、少しずつ変わってきているのが特徴です。
出生サポート休暇
出生サポート休暇は、不妊治療に対応するために導入された比較的新しい制度です。
説明会への参加や通院などに利用でき、有給として扱われます。
年間で最大5日まで取得でき、体外受精や顕微授精といった高度な治療の場合には、最大10日まで認められます。
不妊治療の負担を少しでも軽くするために作られた、ありがたい仕組みです。
妊娠期に利用可能な3種類の休暇
妊娠中の女性が利用できる休暇は、産前産後休暇以外にも複数あります。
代表的なものとして、次の3つの休暇が挙げられます。
1.妊婦健診休暇
2.妊娠障害休暇
3.通勤緩和休暇
妊婦健診休暇
妊娠から出産までの期間に必要な、定期健診のために取得できる休暇です。
妊娠週数に応じて受診回数の目安があり、23週までは4週に1回、24〜35週までは2週に1回、36週以降は毎週1回、出産後1年以内に1回が推奨されています。
もし、通常の有給を充ててしまうとすぐに残りがなくなるため、健診専用の休暇制度は非常に便利です。
妊娠障害休暇
つわりなど、妊娠中の体調不良が重い場合に利用できる制度です。
自治体によって日数は異なりますが、1回の妊娠につき10〜14日ほど取得できるのが一般的です。
症状によっては寝込んでしまうほどつらいこともあり、安心して休める制度があるのは大きな支えになります。
通勤緩和休暇
満員電車など、混雑を避けて通勤・退勤するために利用できるのが、通勤緩和休暇です。
勤務時間の前後を合わせて1時間まで調整でき、たとえば朝は30分遅めに出勤し、夕方は30分早めに退勤する使い方が可能です。
ただし、近年はフレックスタイム制が広がっているため、利用する人は以前より減少しています。
産前産後休暇
出産を控えた女性が取得できる、いわゆる「産休」にあたる休暇です。
民間企業の制度と似ていますが、公務員の産休は条件がさらに良いのが特徴です。
産前8週間と産後8週間、あわせて16週間の休暇が有給として認められ、給与も満額支給されます。
一方、民間企業では「休業」として扱われ、給与の代わりに3分の2程度の手当が支給されるケースが多く、期間も産前6週・産後8週と短めです。
この違いからも公務員の産前産後休暇は、女性にとって非常にありがたい制度だといえます。
子の看護休暇は男性も利用可能
子どもの体調不良や、予防接種のために使えるのが子の看護休暇です。
1年間で最大5日まで取得でき、子どもが2人以上いる場合は合計で10日まで利用可能です。
この制度は男性職員も広く活用しており、性別を問わず子育てに参加しやすい環境が整っています。
休暇以外の休業制度も整っている
子どもが生まれた後は、できるだけ家族との時間を大切にしたいと考える方も多いでしょう。
公務員には休暇制度だけでなく、休業制度も用意されています。
ただし、休暇とは異なり「休業」の扱いになるため、給与が必ずしも満額支給されるわけではない点に注意が必要です。
ここからは、代表的な休業制度を紹介します。
育児休業
育児休業は、子どもを育てるために一定期間仕事を休める制度です。
公務員の場合、子どもが3歳の誕生日を迎えるまで取得できるのが特徴です。
民間企業では1歳までのケースが多いため、公務員のほうが長く育児に専念できる環境が整っています。
休業中は無給となりますが、原則として1年間は給与の3分の2にあたる手当が支給されます。
一時的に収入は減りますが、雇用が失われることはなく、身分が守られている点で安心できます。
部分休業
部分休業は、育児中の職員が勤務時間を短縮できる制度です。
通常の勤務時間の始めか終わりに、1日あたり最大2時間まで短縮できます。
利用できるのは、小学校に入学する前の子どもを育てている場合です。
給与は勤務時間に応じて減りますが、家庭と仕事を両立しやすくなります。
ある県庁では、小さな子どもを持つ女性職員の多くが部分休業を利用していました。
ただし、部署の業務量が多いと利用しづらい場合もあります。
育児短時間勤務
育児短時間勤務は、子育て中の職員が自分に合った勤務パターンを選べる制度です。
内容は部分休業と似ていますが、あらかじめ4つの勤務形態が設定されています。
1.週5日勤務・1日3時間55分
2.週5日勤務・1日4時間55分
3.週3日勤務・1日7時間45分
4.週3日勤務・2日は7時間45分勤務+1日は3時間55分勤務
勤務時間に応じて給与は変わりますが、仕事を続けながら家庭の時間を確保できる仕組みです。
育児とキャリアを両立したい人にとって、心強い制度といえるでしょう。
上司の理解に差があるのが現実
ここまで読んで「公務員は働きやすそう」と感じた方もいるかもしれません。
しかし、制度が整っているからといって、現場が必ず快適であるとは限りません。
たとえば、育児休業を取らずに働き続けた世代が、現在は管理職となっているケースもあります。
その中には「育休は甘えだ」と考える人がいるのも事実です。
また、妊娠中につわりで休もうとする女性に対し「つわりは病気じゃない」と偏見を口にする上司がいる場合もあります。
もちろん、すべての上司がそうではありませんが、価値観の違いがハラスメントにつながることもあるのです。
制度上は女性に優しい職場であっても、現場の雰囲気には差があるという点は理解しておく必要があります。
まとめ
ここまで、女性に公務員をおすすめしたい理由について解説してきました。
・結婚・出産・育児・住宅購入など、将来のライフプランを立てやすい
・女性向けの休暇制度が豊富で、すべて有給として利用できる
・育児に関する働き方を柔軟に選べる仕組みが整っている
・制度は充実しているが、現場ではマタハラや価値観の違いに注意が必要な場合もある
公務員は民間企業と比べて、労働者の権利がよりしっかり守られている職業です。
家庭を持ちたいと考える女性にとって、安定した収入と制度の充実は大きな安心材料になります。
安定と働きやすさを求める方にとって、公務員は非常に心強い選択肢といえるでしょう。
この記事が、公務員という働き方を考えるきっかけになれば嬉しいです。

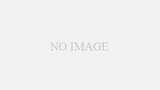
コメント