公務員を目指す人の中には、
「安定した働き方の中で、しっかり休暇を取って私生活も充実させたい!」
と考える方も多いと思います。
特にお盆の時期は、多くの企業や学校が休みに入るため、自分も休みたいと感じやすいでしょう。
一方で「公務員にはお盆休みは存在しない」という話を聞くこともあります。
果たして、実際の職場ではどうなのでしょうか?
この記事では、
・公務員に本当にお盆休みがないのか?
・お盆期間中の職場の実際の雰囲気
・お盆に休暇を確保するための具体的な方法
について詳しく解説します。
公務員にお盆休み制度は存在しない
公務員には、特別なお盆休みは制度として存在しません。
一般的に「公務員は休みが多い」という印象を持たれがちですが、お盆に関しては例外です。
公務員にお盆に休みがないことを、意外に知らない人も少なくありません。
休日は基本的に土日祝日のみ
なぜ、お盆に休みがないのかというと、公務員の休日は、基本的に土日祝日のみと定められているからです。
例外的に年末年始の6日間は特別休暇がありますが、それ以外はカレンダー通りの勤務となります。
そのため、お盆期間には「山の日」という祝日が1日あるだけで、それ以外は平日扱いとなります。
つまり年末年始のように、まとまった休日は設けられていないのです。
代替制度として夏季休暇がある
「お盆に休みがないのは残念」と感じる人もいるかもしれません。
しかし実際には、お盆の代わりとなる休暇制度があります。
それが「夏季休暇」です。
公務員には夏季休暇が設けられており、お盆に重ねて取得することも可能です。
さらにこの休暇は有給扱いとなるため、給与が減る心配はありません。
日数は国家公務員の場合で連続3日間、地方公務員の場合は5〜6日間が一般的です。
7月〜9月に6日間を取得可能
夏季休暇は原則として、7月から9月の間に取得する仕組みになっています。
私が勤務している役所では、この期間に6日間の夏季休暇が与えられています。
必ず連続で取る必要はなく、去年は都合に合わせて分けて休むことができました。
ただし、一部の自治体では「連続して○日以上」という条件が設けられている場合もあるため、勤務先の規定を確認する必要があります。
夏季休暇の利用率はほぼ100%
夏季休暇は、年次有給休暇(年20日付与)よりも取得しやすい雰囲気があります。
私の職場では「必ず夏季休暇を消化するように」という指示が強く、全員が休暇をしっかり取っていました。
そのため取得率はほぼ100%で、誰にとっても取りやすい制度です。
お盆時期の職場の実際の様子は?
夏季休暇を利用すればお盆に休むことは可能ですが、実際にどのくらいの人が休んでいるのでしょうか?
お盆に休む職員は少ない傾向
私が入庁したばかりの頃は「お盆には多くの職員が夏季休暇を取って、職場は閑散とするだろう」と考えていました。
ところが、いざお盆を迎えてみると、休んでいるのは全体の5分の2程度。
思った以上に、出勤している人が多い印象でした。
もちろん部署によって状況は異なりますが、休む人が多い職場でも半数に届かないことがほとんどです。
特に窓口業務のある部署では「最低限○割は出勤すること」といったルールがあるため、出勤者が一定数確保されます。
そのため、多くの職員は7月にまとめて休む、あるいは週に1日ずつ取得するといった形で夏季休暇を分散させていました。
お盆出勤で感じる利点について
お盆に出勤すると、普段とは違う静かな雰囲気を体験できます。
私が実際に勤務して感じた、主なメリットは以下の通りです。
・来客が少ない
・電話の件数が減る
・メールがほとんど来ない
・通勤電車が空いている
・急ぎの案件が少ない
・上司や同僚が不在で集中できる
多くの民間企業がお盆休みに入るため、電話やメールの連絡はぐっと少なくなります。
また「役所も閉まっているだろう」と思われることが多いため、訪問者もほとんど来ません。
その結果、落ち着いた環境で、仕事に集中できる点は大きな利点でした。
お盆勤務にともなう不便や欠点
一方で、お盆に出勤することには、デメリットもあります。
・電話をかけても担当者が不在で業務が進まない
・世間が休みの雰囲気に包まれていて気持ちが沈む
・電車が休日ダイヤで本数が少ない
・上司が不在で急な判断が必要な場面に対応しにくい
特に他の自治体や、中央省庁の担当者も休暇中であることが多いため、連絡が取りづらく業務が滞る場合があります。
また、通勤時に旅行客や家族連れを見かけると「自分も休みたい」という、気持ちが強くなるのも否めません。
ただし、こうした気分になるのは通勤時間くらいで、仕事そのものは静かに集中できる面が多かったです。
夏季休暇を活用してお盆を連休化
お盆の時期、周囲があまり休んでいないと「自分も申請しづらい」と感じることがあるかもしれません。
しかし、夏季休暇は年次休暇よりも取得が推奨されるため、気にせず活用するのが賢明です。
私が勤めている役所では、
・夏季休暇の計画を立てるように指示される
・8月に入ると取得状況を確認される
・9月までに取らない場合は強制的に取得させられる
という徹底したルールがあります。
夏季休暇は、7月から9月の間に必ず消化することが前提なので、お盆の週に5〜6日間まとめて取得しても問題はありません。
「お盆にしっかり休みたい」と考えるなら、この制度を利用して連休を作るのが一番確実です。
また、お盆以外に休みたい日がある場合は、通常の年次休暇を組み合わせる方法もあります。
休暇申請に特別な理由は不要
夏季休暇は「夏の時期に心身を整えて健康を維持すること」を目的としています。
そのため、リフレッシュや体調管理を理由にすれば、問題なく取得できます。
実際には「○日に夏季休暇を取ります」と簡単に申請するだけで、細かい理由を求められることはほとんどありません。
理由を問われた際の答え方の工夫
基本的に理由を深く問われることはありませんが、もし聞かれた場合は軽く答えれば十分です。
例えば「実家に帰省してお墓参りに行きます」といった内容であれば、特に問題視されることはないでしょう。
夏季休暇は制度として保障された権利なので、ためらわずに申請して使うことが大切です。
まとめ
公務員の休日は基本的にカレンダー通りで、お盆休みは制度として設けられていません。
ただし「夏季休暇」を利用することで、お盆の期間に連休を確保することができます。
また、お盆に出勤すれば電話や来客が減って、静かに仕事ができるといった利点もあります。
休みたい場合は、夏季休暇をお盆に合わせて計画的に取るのが効果的。
働くか休むかはそれぞれの判断ですが、自分の体調やライフスタイルに合わせて選ぶのが大切です。
夏季休暇をうまく活用すれば、リフレッシュしながら公務員生活をより充実させることができるでしょう。

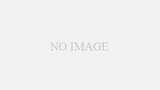
コメント